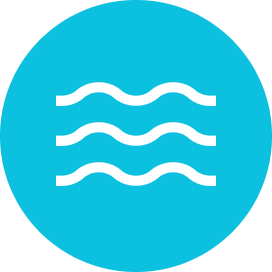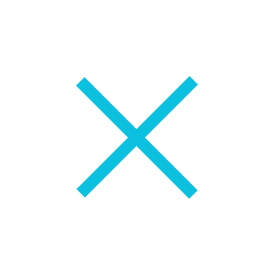知の探究:伊平屋島に息づく「稲の島」の物語
皆さん、こんにちは。今回は、沖縄本島から船で約1時間20分の場所にある、伊平屋島という小さな島について、ちょっとアカデミックな視点からお話ししたいと思います。沖縄といえば、サトウキビ畑が広がる風景を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、伊平屋島は、古くから稲作が盛んな「稲の島」として知られています。なぜこの島だけが稲作を続けてこられたのか、そして稲作がこの島の文化や歴史、さらには神話とどう結びついているのか、その奥深い物語を紐解いていきましょう。
1. 伊平屋島の「今」を知る:稲作の現状とブランド戦略
まずは、伊平屋島の稲作が今どうなっているのか見ていきましょう。島の主要産業である稲作は、特に島の南部に位置する田名(たな)集落を中心に営まれています。沖縄の温暖な気候を最大限に活かし、本州では難しい二期作を行っているのが最大の特徴です。春に植えた稲を7月頃に収穫し、秋に植えた稲を12月頃に収穫するというサイクルで、年に2回、黄金色の田園風景が島を彩ります。
この島で主に栽培されているのは、沖縄の気候に合うように開発された県産米「ちゅらひかり」です。厳しい気候条件の中で育った伊平屋米は、その品質の高さから「てるしの米」というブランド名で県内を中心に高い評価を得ています。この「てるしの」という名前には、後述するように、この島の神話が深く関係しています。
しかし、他の離島と同様、伊平屋島も高齢化や人口減少による担い手不足という課題に直面しています。それでも、島は稲作を単なる農産物ではなく、島のアイデンティティとして守り抜こうとしています。例えば、子供たちが稲作を体験する授業や、観光客向けの稲作体験プログラムなどを通じて、伝統を次の世代に伝えていく努力が続けられています。このように、稲作を中心とした地域振興は、単に米を生産するだけでなく、島の文化と未来を守るための重要な戦略となっているのです。
2. 歴史の証人:琉球王朝と稲作の深い関係
伊平屋島の稲作の歴史は、琉球王国の時代にまで遡ります。古くは中国の文献にも「米を産するに最も佳し」と記されるほど、稲作が盛んな地域でした。この島は、琉球王国を統一した第一尚氏の始祖、屋蔵大主を輩出し、琉球王府と「伊平屋ノロ」という特別な神職制度を通じて密接な関係にありました。ノロは、王府から任命された女性の神官で、島の祭祀や神事を司り、住民の信仰生活の中心的な役割を担っていました。
この伊平屋ノロの重要な職務の一つが、稲作に関わる神事でした。豊作を神に祈り、収穫された米を神に捧げることは、単なる儀式ではなく、王府の支配の正当性や、島の共同体の維持にとって不可欠なものでした。
3. 祭祀に生きる稲作:文化と信仰の交差点
伊平屋島の稲作は、単なる経済活動に留まらず、島の文化と信仰そのものと深く結びついています。稲作のサイクルに合わせて、一年を通してさまざまな祭祀や行事が行われます。
例えば、旧暦8月には、一年間の豊作を神々に感謝し、翌年の豊穣を祈願する豊年祭が盛大に行われます。また、旧暦7月17日には、海神に豊漁と航海の安全、そして豊作を祈願する「ウンジャミ(海神祭)」が古式に則って行われます。ウンジャミ祭には、昭和初期まで島の米でノロの作る「口噛酒」が出されていました。これらの行事は、稲作という共通の営みを通じて、地域の人々が一体となり、コミュニティを強固にする重要な役割を果たしてきました。
また、稲作の神様も存在します。田名集落にある「トゥントゥクー(土帝君)」は、土地の神様であり、農耕社会においては集落の守りとして崇められています。田植えの時期には、この神様への拝みが行われ、干ばつの際には雨乞いが行われました。稲作が人々の生活を支える基盤であったからこそ、自然の恵みに感謝し、神の加護を祈る信仰が深く根付いたのです。
4. 神話に秘められた「てるしの島」の起源
伊平屋島は「てるしのの島」と呼ばれますが、この「てるしの」は太陽と神々を意味する言葉が転じたもの、あるいは、琉球の開闢神話に登場する「太陽神」であるという説があります。この神話と稲作は、分かちがたく結びついています。
日本の神話では、天孫降臨の際に稲穂が地上にもたらされ、稲作が始まったとされます。沖縄でも同様に、神々が稲作を授けたという開闢神話が語り継がれてきました。伊平屋島にも、稲作の起源を語る独自の口伝があり、島の稲作は神々から授けられた神聖なものであるという信仰が育まれてきました。これは、稲作が単なる生産活動ではなく、共同体の存在そのものと深く結びついた神聖な営みであることを示しています。
特に、稲作の中心地である田名集落には、稲作にまつわる神話が数多く残されています。その一つに、遠洋漁業に出た夫の帰りを待ちわびる妻の物語があります。夫の無事を祈りながら、妻は機織りをしていました。その布が水平線まで届くほど長くなった頃、夫は無事帰ってきたといいます。この物語は、夫の無事を願う信仰心と、日々の勤勉な農耕生活が一体となっていることを象徴しており、島のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。
さらに、田名集落には、神事のみに用いられる「神田(しんでん)」が存在します。ここで収穫された米は、神様への供物として用いられ、厳格に管理されています。神田の存在は、現代においても稲作が単なる経済活動ではなく、神聖な儀式と一体化したものであることを物語っています。
結び
伊平屋島の稲作は、沖縄という特殊な環境の中で、人々の知恵と努力、そして深い信仰によって育まれてきた、非常にユニークで貴重な文化的遺産です。サトウキビが主流の沖縄において、稲作を維持し続けてきたこの島の人々の強靭な精神性には、知的な探究心をくすぐられるものがあります。
稲穂が風に揺れる田園風景は、単なる美しい景色ではありません。それは、島の歴史、文化、そして神話が織りなす壮大な物語の象徴なのです。現代的な課題に直面しながらも、伊平屋島が「稲の島」としての誇りを持ち続ける限り、この物語はこれからも語り継がれていくことでしょう。
伊平屋島を訪れる機会があれば、ぜひこの田園風景をただ眺めるだけでなく、そこに込められた深い歴史と文化、そして人々の思いを感じ取ってみてください。きっと、新たな発見があるはずです。