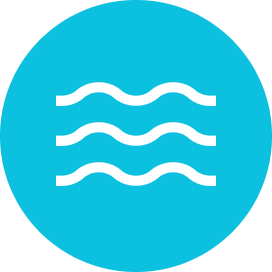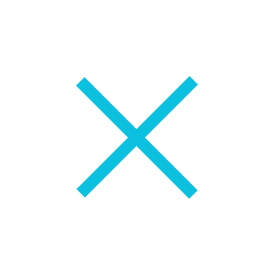ザワワ……沖縄の広大な畑を揺らす、あのサトウキビ(ウージ)の音。
それは、ただ風が葉を擦る音ではない。大地が記憶する「声」そのものである。
沖縄の原風景を形作るこの植物は、単なる作物ではない。その茎に凝縮された「甘さ」によって、琉球王国の光と影、栄華と悲哀の両面を紡ぎ、この島の「宿命」を背負わされてきた存在だ。
これは、一筋の茎(ウージ)に刻まれた、琉球の甘くもほろ苦い記憶の物語。その前編を紐解こう。
第1章:原産不明、すでにあったサトウキビ(伝来と潜在)
ウージがいつ、どのようにして琉球の土に根付いたのか。その正確な起源は、歴史の霧の中だ。一説には15世紀の記録にその名が見えるというが、当時のウージはまだ「少し甘い草」に過ぎなかった。
その茎に、灼熱の太陽エネルギーを「甘さ」として蓄える類稀な力。それがやがて島の運命を左右し、政治と経済の奔流を呼び込む「鍵」となることを、まだ誰も知らずにいた時代である。
第2章:錬金術の獲得(儀間真常と黒糖の誕生)
時は17世紀初頭。琉球王国は、大国・明と、北の薩摩藩という二つの力の間で、自らの針路を模索していた。この時代の閉塞感の中、島の未来を見据える「先見者」がいた。琉球五偉人の一人、儀間真常(ぎましんじょう)である。
彼が注目したのは、ありふれた植物ウージに秘められた無限の可能性だった。
1623年。儀間真常は、当時「国家機密」であった製糖技術を求め、中国・福州へ人を派遣する。これは単なる技術導入ではない。ウージの汁という「液体」を、富の源泉である「個体」へと変える技術。まさしく、太陽の光を「黒い金塊(黒糖)」へと変える「錬金術」の探求であった。
このミッションの成功により、琉球は新たな価値の源泉を手に入れた。ウージは覚醒し、その甘さは島の経済を動かす「力」となった。
第3章:甘美なる呪縛(薩摩藩と黒糖地獄)
だが、その甘い香りは、北の「影」を強く呼び寄せることになる。
儀間真常の偉業に先立つこと14年(1609年)、琉球は薩摩の武力侵攻を受け、実質的な支配下に置かれていた。薩摩藩は、この「黒い金塊」が持つ莫大な経済的価値を見逃さなかった。
やがて「貢糖」というシステムが確立される。それは、ウージの甘さを媒介とした、琉球への「甘美なる呪縛」の始まりだった。
農民は、自らの命を繋ぐ米や芋の畑を潰し、ウージを植えることを強いられた。朝から晩まで過酷な労働で生み出された黒糖は、そのほとんどが薩摩藩によって「年貢」として持ち去られていく。
「黒糖地獄」
ウージは島の命を育む糧から、支配の対価を支払うための「緑の通貨」へと、その宿命を変えられてしまった。
第4章:北端の聖域(伊平屋島の選択)
この甘い呪縛が島々を覆い尽くす中、沖縄本島北西に浮かぶ「てるしの(太陽神)」の島・伊平屋島は、異なる運命を辿っていた。
神々が降り立ったという伝承が色濃く残り、「琉球稲作発祥の地」とも言われるこの島は、古来より「稲作」を何よりも神聖な営みとしてきた。
他の島々が黒糖生産の重圧に喘ぎ、「緑の通貨」の生産に追われる間も、伊平屋は頑なに「米」の文化を守り続ける。この島がウージを主要作物として本格的に受け入れるのは、薩摩の影が薄れ、琉球王国が消滅した後の明治30年代。
伊平屋は、歴史の激流から一歩引いた「聖域」として、自らの意思で「近代」と共にこの植物を選び取った。その選択は、この島の孤高の精神性を象徴しているかのようでもある。
第5章:近代という名の再編(明治維新と製糖工場)
明治維新。琉球処分。「薩摩藩」という具体的な支配者は消え、琉球は「沖縄県」として近代国家日本に組み込まれた。
だが、ウージを巡る宿命は終わらない。むしろ、形を変えて強化された。
「富国強兵」「殖産興業」の論理のもと、製糖は国家の重要産業と位置付けられる。薩摩藩による前近代的な搾取は、蒸気機関で動く近代的な「製糖工場」による、より効率的な生産・集積システムへと再編された。
農民とウージを縛る鎖は、より巧妙に、より大規模になった。ウージは沖縄の経済を支えると同時に縛り続ける「緑の鎖」として、戦前の時代までその役割を担い続けたのです。
(後編へ続く)
この甘美なる呪縛は、戦前で終わることはなかった。「鉄の暴風」がすべてを焼き尽くした後、ウージは再び沖縄の土に何を宿すのか。後編では、焼け野原から立ち上がり、今度は「世界情勢」という新たな奔流に巻き込まれていくウージの物語を紐解いていこうと思います。