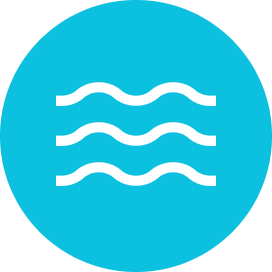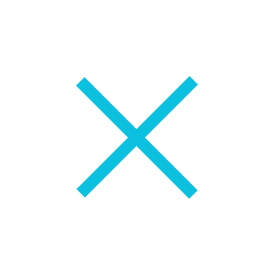位置
東シナ海に浮かぶ沖縄最北端の離島村。
「琉球弧」と呼ばれる九州から台湾に掛けて連なる列島の中ほど、沖縄本島の最北端、辺戸岬の北西20km、鹿児島県の最南端、与論島とほぼ同緯度、那覇から北へ約100kmの地点にあり、かつては伊是名島はじめ付近の島々と共に「伊平屋七隠れ」と呼ばれていました。

かたち
島の周囲は約40km、南西から北東にかけて細長く、幅は広いところで3㎞程度、長さは約15kmあります。
そこに隆起した標高200mを超え6つの山が連なり、沖縄本島から見ると、まるで海から山脈が突き出たように見えます。
伊平屋島と野甫島の2島で構成され、橋で繋がっています。周囲は珊瑚礁に囲まれ、山と山の間の狭い平地に田畑と5つの集落が点在し、約1,200名の島民が暮らしています。

歴史
島の歴史は古く、縄文前期に当たる紀元前4500年頃の沖縄土器が久里原貝塚で見つかっている。
東南アジアと日本本土を結ぶ海の道の要所として、黒潮に乗って琉球弧を島伝いに小舟で行き来する旅人たちの寄港地となり、様々な文明や文化を吸収し、またおもてなしの心が育まれました。

伝統文化
伝わった文明の大きな特色のひとつが稲作です。
沖縄の離島では珍しく山が多いことから水が豊富で、温暖な気候と相まり、水稲栽培に適していたことから、早くから稲作が伝わりコメ作りが盛んに行われてきました。
また、豊年祭、綱引き、ウンジャミ、世願(ゆうにげ)など五穀豊穣を祈る伝統行事も数多く行われます。

神話の舞台
海の幸、山の幸に恵まれたこの島の景色は、日本神話に登場する神々の住む楽園、高天原(たかまがはら)さながらで、天岩戸の描写に近いクマヤ洞窟の存在もあり、江戸時代中期の考古学者、藤貞幹はその著書「衝口発」で神武天皇の出生地は伊平屋と唱えたことも頷けます。
また、第一尚氏の祖、尚思紹の祖父にあたる屋蔵大主(やぐらうふぬし)は伊平屋の我喜屋の人で、息子の鮫川大主(さめかわうふぬし)が佐敷に渡り大城按司の娘を娶り思紹を設けたと言われています。

素朴な原風景
近代に入り、大型船や飛行機の出現で素通りされ、次第にこの孤島は時代から取り残されていきました。
ただそれが故に開発から免れ、手つかずの自然や昔ながらの伝統文化が今でも多く残っています。